2025年12月01日(月)10:09STスポット

かもめマシーンは日本国憲法や当時の政治家たちの演説を用いた『俺が代』や、2011年の福島第一原子力発電所事故後に福島県の路上で上演された『福島でゴドーを待ちながら』、そして電話越しに他者の声を聴く『電話演劇シリーズ』など、「わたしたちは何を、どう受け止めているのか?」という問いを観客の前に静かに、しかし鋭く差し出してきたカンパニーだ。
そのかもめマシーンがいま「南京大虐殺」をめぐって、何を、誰に、どのように届けようとしているのか。2022年から東京・沖縄・台湾・UKなどで国内外で3年間にわたって展開してきた『南京プロジェクト』。その集大成として、2025年12月にSTスポットで上演される最新作『南京プロジェクトvol.6』の創作が、今稽古場で進んでいる。
ひとつのことにこれほど長い時間をかけ、形を変えながら持続して向き合い続けられることは凄まじい。同時にこのプロジェクトはおそらく「終わらない」のかもしれない──そう思わせるような、独特の静けさと緊張の言葉の時間が稽古場には流れていた。
取材・文:木村友哉(ザジ・ズー/仮設社/ザ・シティイ) 取材日:11月17日
南京プロジェクトについて――語れなさから始まった3年間
 『南京プロジェクトvol.5』@ランカスター大学(2025年4月)
『南京プロジェクトvol.5』@ランカスター大学(2025年4月)
『南京プロジェクト』は萩原雄太さんの「南京大虐殺についての作品をつくりたい」という、ある意味では個人的な関心から始まった企画だという。けれどもその提案は、メンバーから強い反対を受けるところからスタートした。中国と日本でまったく異なる歴史教育のあり方、中国の人と南京大虐殺について語ることの難しさ──そうした懸念が噴き出すなかで、「そもそも、なぜわたしたちはこの出来事を扱いたい/扱いたくないと感じるのか」ということから問い直すプロジェクトになっていった。
萩原さんたちはまず、自分たちの「知らなさ」と向き合うところから始める。日中戦争から南京大虐殺に至るまでの年表づくり、日中両方の教科書の読み比べ、中国からの留学生へのインタビューなどを通じて、「わたしたちは被害者なのか加害者なのか」「なぜ南京のことだけ、こんなにイメージできないのか」といった問いを稽古場の身体レベルで引き受けようとしてきた。
その過程は東京・早稲田小劇場どらま館でのワークインプログレス(2022年)、那覇・わが街の小劇場での滞在制作(2023年5月)といった場を経て、観客との対話のかたちを探る試行へと広がっていく。横浜・高架下スタジオ Site-D 集会場での『南京プロジェクト vol.4 <再演>教育委員会』(2024年)では、日本側の公式文書や議事録を観客が音読することで、「日本語で南京大虐殺を語る」とはどういうことかを可視化するが行われた。さらに、2025年4月にはイギリス・ランカスター大学で vol.5 を上演し、同年夏には実際に南京の街を訪れてリサーチを行うなど、場所を変えながらプロジェクトは少しずつ形を変えて続いてきた。
『南京プロジェクト』は、ひとつの作品に向かう制作というよりも、「日本人として南京大虐殺とどう向き合うか」をめぐる長期的な場として続いているのだ。その〈終わらなさ〉を抱えたまま、稽古場の時間は進んでいた。ここからは、その一端を伝えてみたい。
『南京プロジェクトvol.6』稽古場レポート──森下スタジオにて
 本作の稽古風景
本作の稽古風景
1. 稽古場の朝──静かに立ち上がる時間
2025年11月17日の午前。
東京都江東区にある森下スタジオの一室で、『南京プロジェクトvol.6』の稽古が行われていた。時間帯は10:00〜15:00。わたしが稽古場に到着したときには、すでに構成・演出の萩原雄太さんとBeri Juraic(ベリ)さんが、ゆっくりと準備を進めていた。
ベリさんは前回のランカスター大学でのvol.5にも関わっており、日本と海外をつなぎながらこのプロジェクトに並走してきた存在だ。そのこと自体が、この企画が「日本の内側だけの問題」ではないことをさりげなく示しているように感じられた。
ほどなくして、出演者の清水穂奈美さんと伊藤新さん、そしてスタッフ陣がぞろぞろと集まってくる。
「いつもは3〜4人なんだけど、今日は人が多いんですよ」と萩原さんが笑いながら言う。
けれど、誰かが前に立って号令をかけるような「ファシリテーター」はいない。各自が思い思いに荷物を置き、ストレッチをし、ときどき近況を交わしながら、それぞれのペースで稽古の準備を進めていく。
その光景は、長く続いてきたプロジェクトの現場というよりも「長い長い蓄積した時間」を感じた。
南京プロジェクトとして積み重ねてきた3年間の時間と、かもめマシーンというカンパニーがこれまで育ててきた関係性がすでに日常のルーティーンとして身体に染み込んでいる。誰かが仕切らなくても、必要な会話が必要なタイミングでぽつぽつと立ち上がり、全体の温度が少しずつ上がっていく。
静かだが、決して止まってはいない朝の時間。
この「静かに立ち上がる」気配が、南京プロジェクトの空気を象徴しているように思えた。
2. 俳優ふたりの登場が、空気の密度を変える
11:00ごろ。
特段「では始めます」といった号令がかかるわけではない。誰かが椅子に座り、誰かがノートPCを閉じる。その小さな動きの連鎖が、ゆっくりと「稽古開始」の合図になっていく。
この上演は、俳優ふたりの佇まいそのものが始まりだ。
黒電話とロッキングチェア、そしてラジオ。簡素だが、どこか見覚えのある生活の断片のような舞台セットの中に、清水穂奈美さんと伊藤新さんがすっと立つ。風に揺れる木の葉のように静かに、しかしたしかに「この部屋で暮らしている家族」として、そこに居続ける。
ふたりがそこに立った瞬間、さっきまで「ただの稽古場」だった部屋が、別の空間に変わる。スタジオの外から聞こえてくる車の音や、椅子のきしむ音でさえ、この部屋の中で起きている出来事の一部として聞こえてくるようになる。空気の密度が少しずつ変わっていくのが、肌で感じられる。
やがて、それぞれの準備が整い、最初の通し稽古が始まる。
ラジオからは、淡々と天気予報の声が流れる。日本各地の天気と波の高さが読み上げられていく、その列のどこかに「南京」という地名が何度も繰り返し混ざり込む。部屋の中の時間は「いま・ここ」から決して逸脱しないのに、言葉に引き寄せられて、観客(になるはずのわたしたち)の意識が引っ張られていく。
3. 最初の通しが突きつけた「知っているのに知らない」感覚
この日の通しは、「いい感じ」という言葉ではとても足りない、複雑な実感を私に残した。
南京大虐殺について「頭では知っている」はずだ。
教科書やドキュメンタリーで、その存在を学んだことはある。けれど、その出来事と自分自身の生活や身体が具体的にどんなふうにつながっているのかを考えたことがあるかと問われると、途端に言葉に詰まる。
この上演が描き出そうとしているのは、まさにその「知っているのに知らない」という状態だ。
南京大虐殺をめぐるあらゆる言葉は、わたしたちの前にすでに「歴史」という大量生産された物語として存在している。けれど、それをただ引用し直すのではなく、「いまこの部屋で暮らしている誰かの生活」と同じレイヤーに並べ直していた。
通しを見ながら、わたしは自分がいかにこの出来事を「教育の中のフィクション」のように扱ってきたかを思い知らされた。
知っているけれど、知らない。
知識としては把握しているつもりだった年号や出来事が、目の前の俳優の沈黙や、ロッキングチェアのわずかな揺れとぶつかったとき、まったく別の重さを帯びてこちらに返ってきたのだ。
安心してほしいのはこの上演が「新たな正しさ」を押し付けてくるような時間ではないということだ。むしろ、観客がそれぞれに抱えている「知らなさ」や「語れなさ」をそのまま持ち込んでいいのだと示してくれるような、静かだけれど、居心地の良い時間だと感じた。
4. 通し後の議論──「どう上演するか」と「なぜ上演するか」
通しが終わると、少しの休憩ののち、そのまま話し合いに移行する。
舞台美術のセッティングについての具体的な確認から始まり、さっき見たばかりの通しをどう受け止めたのか、お互いの実感をすり合わせるような時間が続く。
「ゴミ箱の位置は本当にこの場所なのか」
いわゆる「演出メモ」にあたるような話題ももちろん出てくる。ただ、この稽古場ではそれだけで終わらない。
「その責任を、どうやってみんなで取りにいく形にできるのか」
そんな問いが、ごく当たり前のこととして稽古場に寄り添っている。上演で描かれる家族と同じように、この稽古場で「誰がどんな位置に立つのか」も上演と地続きの問題として扱われているようだった。
ホワイトボードに舞台の平面図を描き、黒電話や椅子、ラジオ、観客の位置をどう配置するかを全員で「絵」にしていく。誰かが描いた線に別の誰かが書き足し、また別の誰かが別案を描く。ひとつの図のなかに、複数の視点が重ね書きされていく。
まるで同じモチーフを囲んで、全員でデッサンをしているような時間だ。
その線の違いを見比べることで、「この上演をどこから、どう見たいのか」というそれぞれの目線が露わになっていく。気づきが共有されるたびに、アイデアは転がり、コミュニケーションとともに上演の輪郭が少しずつ磨かれていく。
さらに、話し合われているのは「どう上演するのか」だけではない。
気づくと、「なぜ上演するのか」という根本的な問いにもいつのまにか話題が移っている。演出・俳優・スタッフという役割を固定したままではなく、ときに立場を移動しながら、それぞれの目線で南京大虐殺と上演との関わり方を確かめていく。
役割が変われば、見えるものも変わる。
その前提を稽古場という場所として共有しようとしているのだと感じた。
5. 言葉に飲み込まれないために──座談会へと続く思考の場
こうしたプロセスの一部は萩原さんによるnoteの発信などを通じて、すでに外部にも共有されている。興味がある方には、ぜひ一度読んでみてほしい。そこに書かれているのはいわゆる作品の宣伝文句ではない。彼らのこれまでの行動がそこには記録されている。
その文章を読むと、このプロジェクトにとって「考え続けること」自体がすでに実践であり、上演の重要な一部なのだということがよくわかる。
本作の第二部として予定されている座談会も、この延長線上にある。
上演の感想を述べ合う場というより、「南京事件をどう思うのか」を観客と共有する場として構想されているという。
「見たことについて喋ることはできる。けれど、これを元にして何を喋ればいいのか、というところで立ち尽くしてしまう」
稽古場のどこかでこぼれたその言葉は、このプロジェクト全体の難しさと誠実さをよく言い当てているように思えた。
南京プロジェクトは「語れなさ」を無理に乗り越えようとするのではなく、その状態にいったん留まり続ける。その上で、それでもなお誰かとことばを交わそうとしているのだ。それはこの稽古場を訪れて、かもめマシーンは対話の可能性を信じているからだと感じた
どうやるのか。
なぜやるのか。
上演の手つきと、その根拠をめぐる往復運動。
その揺れ続ける運動そのものが、『南京プロジェクトvol.6』の森下スタジオでの稽古をかたちづくっていた。
おわりに──終わらないかもしれないプロジェクトの現在地
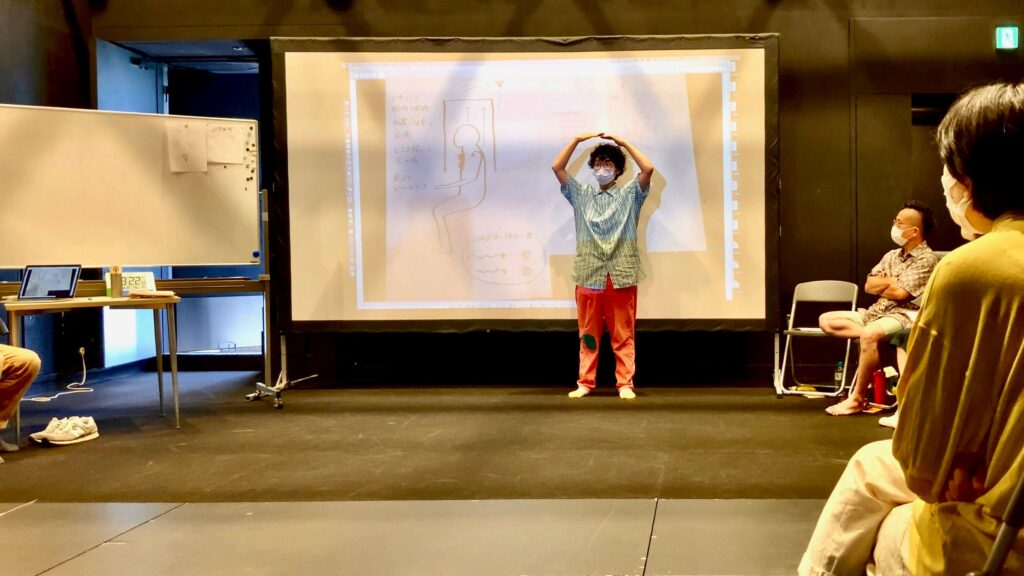 ワークインプログレス@早稲田どらま館小劇場(2022年8月)
ワークインプログレス@早稲田どらま館小劇場(2022年8月)
稽古が終わり、森下スタジオにゆっくりと静けさが戻り始めたころ、萩原雄太さんとBeri Juraic(ベリ)さんに、このプロジェクトについて話を聞いた。
萩原 最初は、こんなに長く続くとは思っていなかったんです。
Beri 僕はこのプロジェクトは「終わらない」と思いました。
ふたりはそう言って、少し笑った。
当初は1本分の新作をつくるためのリサーチとして、ある程度区切りのついたプロジェクトになるはずだったという。ところが、実際に動かしてみると、むしろそこから問いが増えていった。「南京をテーマにしたい」と口にしたときに、カンパニーメンバーから強い反対を受けたことも含めて、このプロジェクトは常に「簡単には進めない」という手触りとセットで続いてきた。
それでも三年間、東京・沖縄・台湾・UK、そして南京へと場所を移しながら、このプロジェクトは続いてきた。
萩原さんが見ているのは、「日本人だけで作品をつくる」段階のその先だ。まず自分たちの「知らなさ」や「ヒヤヒヤする感じ」「負い目」を引き受ける時間を経たうえで、いずれは中国のアーティストたちとも一緒に作りたいと話していた。
それは共作をするという意味ではなく、「日本人だけで完結させない」ということを、このプロジェクトのかたちとして引き受ける、ということでもあるだろう。
萩原 もっといろいろな人と南京大虐殺について話したい
南京に直接関わる人だけでなく、いま日本に生きているさまざまな人たちと、「なぜ自分たちはこの出来事を知らないまま来てしまったのか」「どのくらいの距離で引き受けられるのか」を、一緒に考える場を増やしていきたい──。
今回の上演と第二部の座談会はそのためのひとつの試みなのだと思う。
このプロジェクトは、おそらくどこかできれいに「終わる」ことはないのかもしれない。
だからこそ、『南京プロジェクトvol.6』の森下スタジオでの一日は終わりのない問いの、そのときどきの「現在地」をそっと切り取るような時間だった。

【公演情報】
【提携】かもめマシーン『南京プロジェクトvol.6』
2025年12月4日(木)-12月8日(月)
公演詳細:https://stspot.jp/schedule/?p=14306
かもめマシーン
2007年設立。「公共」という概念をいかに身体化していくかを中心テーマとしながら作品を創作。主な作品に、『福島でゴドーを待ちながら』、日本国憲法をテキストにした『俺が代』、『しあわせな日々』(サミュエル・ベケット作)など。コロナ禍以降は黒電話を用いた「電話演劇シリーズ」を発表。また、南京大虐殺についてのリサーチを開始し、これまで日本、台湾、イギリスでプロジェクトを展開している。